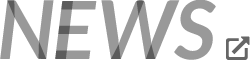【No.023】税理士科インタビュー 「法人税法編①」
2017.09.19
こんにちは緒方です![]()
土曜日~月曜日までを(短い)シルバーウィーク![]() として、(勝手に)ブログをお休みしていました
として、(勝手に)ブログをお休みしていました![]() !
!
台風![]() は日本を縦断
は日本を縦断![]() したようで、最後は北海道にまで上陸したそうです
したようで、最後は北海道にまで上陸したそうです
(北海道への上陸は多くはありませんが、珍しいほどのものではありません)
熊本校周辺は、葉っぱ等が散らばっていた程度![]() で、そこまでの被害はありませんでしたが、
で、そこまでの被害はありませんでしたが、
九州内でも地域によってはかなりの被害が出た場所もあるようです
↓台風直後の熊本学周辺の雲の様子

被害地域の、一日も早い復興と支援を願うばかりです。
さて、本日は3日ぶりの久々の更新![]() のため、書くこと
のため、書くこと![]() が溜まってしまっていますが、
が溜まってしまっていますが、
とりあえず、学生の様子をお伝えしようと思います![]()
それでは、本日のブログ、スタート!
講師ブログNo.023
「税理士科インタビュー『法人税法編①』」
「本日の1年生は、私の授業でした![]() !」
!」
…というセリフを、何度言ったことでしょう。。![]()
いつも私の授業しかご報告できず申し訳ありません。。![]()
と、いうことで!
本日は、経理本科ではなく、税理士科の方々にインタビュー![]() してみました!
してみました!
まずは先生へのインタビュー!
本日の学生の授業は![]() 法人税法
法人税法![]() ですので、専任の赤池先生に質問です
ですので、専任の赤池先生に質問です![]()
※法人税法は、企業の利益に対して課せられる税金について学ぶ科目です
Q.本日の授業内容はどんなものですか?
減価償却という論点です![]()
ここでは、建物![]() などの固定資産を買ったときに、一括して費用
などの固定資産を買ったときに、一括して費用![]() (損金)にするのではなく、
(損金)にするのではなく、
数年に分けて少しずつ費用化(損金算入)するための計算方法を学習します![]()
Q.授業のポイントは何ですか?
会計上は、減価償却の方法は合理的な理由があれば、ある程度企業が自由![]() に決められますが、
に決められますが、
税務上は、減価償却を行うために必要な年数(耐用年数)が法律で定められています![]()
さらに、費用計上(損金算入)額の限度額も設けられているのです![]()
この点について、なぜ法律で計算方法を細かく規定しているのか、
これを理解することがポイントとなりそうです。
Q.授業中の学生の様子はどうですか?
今日の内容は基本的ですが、量が多く、多少悩む![]() 部分もあるので、初受講の学生はかなり大変そうでした
部分もあるので、初受講の学生はかなり大変そうでした![]()
ただ、2年目の人※にとっては、基本的な内容だったので、問題なかったと思います![]()
※税理士科の授業は、1年スパンで行われ、試験終了後も同じ内容をもう一回受講する学生が多いのです
ありがとうございました![]()
それでは続いて、学生にインタビューしたいと思います![]()
まずは和田くん(1回目の受講)![]()
Q.授業のポイントは何でしたか?
ポイントは、「会計上の損益計算の目的と、税務上の所得計算の目的の違いによって、
費用計上額(損金算入額)がどう変わってくるのか」ということではないでしょうか?
ムムムなるほど。。。![]()
難しい返しですが、赤池先生が教えてくれたポイントに近い的確な答えです![]()
要するに、「目的の違いによって、会計と税務で費用(損金)額が変わることがポイント」
だということでしょう![]()
丸暗記ではなく、頭で理由を考える、正しい学習をしていますね![]()

次は丸山さん(2年目の受講)に聞いてみましょう![]()
Q.本日の授業の手応えはどうですか??
昨年、少しですが法人税法の授業を受けていました![]()
その時はわからなかった![]() ことが、今日の授業で深めることができたのでよかったです
ことが、今日の授業で深めることができたのでよかったです![]()
ありがとうございました!深められたことはいいことですね!
繰り返しが大切だということですね![]()

最後に、仲間さん(初受講)に聞いてみたいと思います![]()
Q.本日の授業を理解するための具体的な方法は??
色々ありますが、今のところ私が行っているのは、
①ノート![]() を何度も見返す
を何度も見返す
②計算を解く時にも理論を併せて確認する![]()
③個別問題を解きこなす![]()
ということです。
特に、問題を解く![]() と、自分がわかっていなかった論点が浮き彫りになるため、理解が深まります
と、自分がわかっていなかった論点が浮き彫りになるため、理解が深まります![]()

なるほど。。学生たちも、しっかり考えた学びを実践しているのですね…![]()
そして全員が、仕事に使える税法を学びたい![]() という姿勢があるのが頼もしい限りです
という姿勢があるのが頼もしい限りです![]()
さらに!学生に共通しているのは「真剣さ 」です!
」です!
息抜き は非常に大事ですが、息を抜きすぎては苦しい
は非常に大事ですが、息を抜きすぎては苦しい ものです。
ものです。
毎日の真剣さがあってこそ、息抜きの効果がでてきますね
これからも、壁に当たることも多いと思いますが、学校全体を、全員でさらに盛り上げていきましょう![]()
本日は、税理士科へのインタビューでした![]()
(これからも不定期でお送りします)
それでは、また明日!!